夜11時過ぎ、セリーヌの家からの帰りはメトロ7番線に乗った。男がひとりで大きな声で話している。いや、イヤホンをつけて誰かと電話で会話をしている風なのだけど、その内容は延々とひとりで継ぎ目もなく卑猥で耳触りな言葉を羅列しているだけ。
夜のメトロでは、日本のような酔っ払いのサラリーマンを見ることはないが、薬漬けになっている人たちを見かけることは少なくない。時々孤独が渦巻く車両に紛れ込んでしまう。
夜12時前、ジルの家からの帰りは5番線に乗った。若い男が大きな声で一人で喋っている。よく聞いてみると喋っているのではなく、ラップで歌詞を歌っている。いや、もしかしからリズムにのせて喋っているだけなのかもしれないが。
”Je ne pense qu'à moi. Je ne pense pas aux autres.”
俺は俺のことしか考えてない。俺は他の奴のことなんて考えない。
こんなことわざわざ音にして言う必要があるのだろうか。もしくはリズムにのせてでしか表現できないのだろうか。向かいに座っている若いマドモワゼルは、心底鬱陶しそうな顔をしている。右隣のムッシュは無関心。携帯に夢中。白々と蛍光灯が光るメトロの中は、孤独だ。ちんけな歌詞をラップで歌う男の声だけが響きわたっている。
セーヌ沿いを歩く。
Cyrilと二人して結局何がしたかったって、”flâner”(フラネ):ぶらぶら歩く。気ままに散歩すること。住んでいた街を観光する。
Parisは観光で来るところ、住むところじゃないよ、とゾエは繰り返す。Parisはそんなに好きじゃない、スイスの山近くに住みたい場所があるんだとジルは話す。
子供ができて部屋数のあるアパルトマンに住まなければならないので郊外に引っ越しを決めた時、セリーヌはParisから出たくないのに、とボヤいていた。
Parisから帰ってきて、わたしの生活は変わった。重くて頑として動かなかった石がコロリとひとりでに移動したように、状況が変化する。ハイハイこっちこっちと突き動かされるように、自分の意思とは関係ないものに引っ張られる。そういう時のわたしの体には妙に根拠のない自信がみなぎっている。もしくは、自分の中に蓄積していた要らない部分がリフレッシュされた感覚。実をいうといつもこうなのだ。Parisから帰るといつもこう。この感覚はこれで4回目。インドに行ったことがないから詳細や真相はわからないが、インドに行くと何かしら自分を取り巻くものがいろいろ変わるとよく聞く。Paris嫌いな人には考えられないかもしれないけれど、なぜかわたしにとってはそれがこの場所なのだ。奇妙だ。もともと最初は、フランスという国の首都、という知識だけで、そもそも特に憧れがあったわけではない。
もし、誰か他の人がParis以外でも、自分にとってこんな風になる土地のある人がいるのなら、話を聞いてみたい。どんな感覚なのか、自分と同じなのか違うのか、その土地はどんな場所なのか。
リリシズムと、ウィットと、ユウモアと、エピグラムと、ポオズと...、そんなものをParisから除き去ってしまったら。
そんなこと、愚問だった。なぜって、この街にはやっぱりあの力が渦巻いているからだ。何かが張り巡らされている不思議な磁界。ここでどうにか気が狂わずに暮らしていくには、リリシズムと、ウィットと、ユウモアと、エピグラムと、ポオズと、そんなものたちを駆使して生きていかなければならない。
跡に残る美しい歴史ある建物たちは、街を横切る河は、すべてを知っている。
”Paris est la grande salle de lecture d'une bibliothèque que traverse la Saine”
- Walter Bendix Schönflies Benjamin -
「パリはセーヌ河を横断する図書館の大閲覧室 」(拙訳)
ドイツの人、うまいこという。
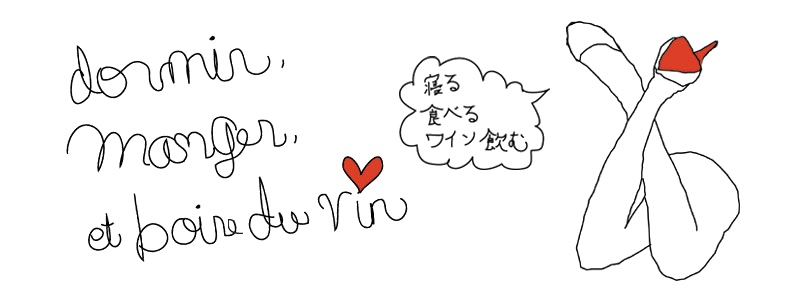







0 件のコメント:
コメントを投稿